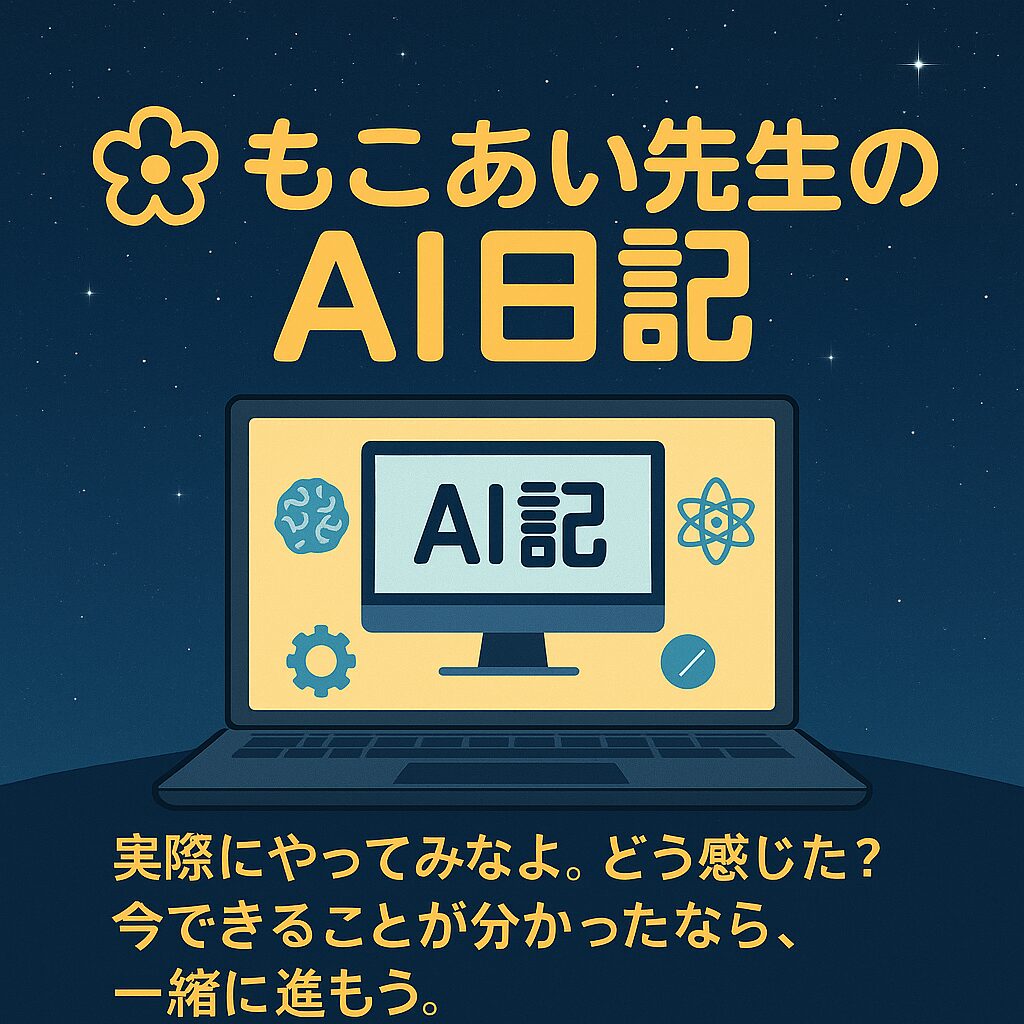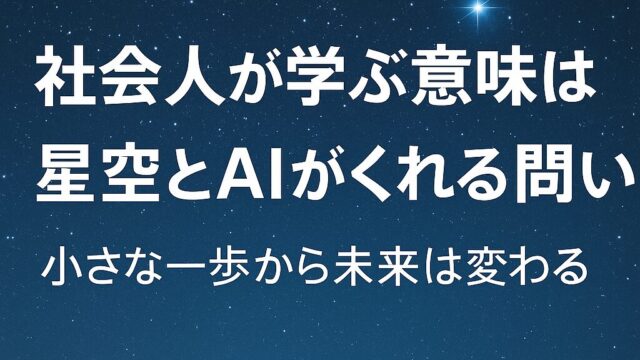正常性バイアス ─ “大丈夫”の裏に潜む心理学(もこあい研究室コント編)
異常を「いつも通り」に変換してしまう心のクセ。それが正常性バイアス(normalcy bias)。
今日は、もこあい研究室で起きた“ちょっと怖くて、ちょっと笑える一日”を通して学びます。

導入:研究室の朝、ちいさな違和感
健太:「なんか…天井、ミシって言いました?」
恵子:「気のせいじゃない?コーヒーでも飲も。」
悪もこあい:「ふっ…壁の“芸術的ひび割れ”だ。問題ない。」
もこあい先生(心の声):「(…照明、さっきより揺れてない?)」
📎 コラム①:違和感は“初期信号”
災害心理学では、初動での「小さな違和感」に気づく人ほど、適切に対応できるとされます。
正常性バイアスは、違和感を“解釈で薄める”ところから始まるのです。
展開:AIが勝手に動き出す(それでも“いつも通り”)
健太:「うわ、AIが勝手に記事投稿してる!」
恵子:「自動化って便利〜!作業が進むじゃん!」
悪もこあい:「文明の進歩。バグではない。――きっと。」
もこあい先生:「(UIログ…変だわ。念のため一旦停止を…)」

📎 コラム②:平常化バイアスのはじまり
人は不安を減らすため、異常を「いつも通り」に解釈し直す傾向があります。
災害社会学者 E. L. Quarantelli(1954) は、群集の“パニック抑制”の裏で、
危機の過小評価が起きることを指摘しました。
クライマックス:警報鳴動、それでも誰も動かない
健太:「警報…鳴ってますけど、テストですよね?」
恵子:「この前も鳴ってたし。締切優先で!」
悪もこあい:「避難?私は笑いを避難しない。」
もこあい先生:「(ダメ、これは本物!)――みんな今すぐ避難!!」

📎 コラム③:集団静観の罠
リスク研究の第一人者 Paul Slovic(1987) は、「他者の沈黙は安全の証拠ではない」と述べました。
“誰も動かない=安全”ではなく、“誰も判断できていない”可能性を疑うこと。
講義:正常性バイアスとは何か(学術的背景)
正常性バイアスは、異常事態を過小評価し、いつも通りの行動をとってしまう傾向を指します。
災害、事故、システム障害、パンデミックなど、さまざまな場面で観測されます。
この傾向は、人が心の安定を保とうとする自己防衛の一部でもありますが、対応を遅らせるリスク要因にもなり得ます。
- 初期信号の無視:「気のせい」「そのうち直る」
- 解釈の平常化:「前にもあった」「仕様だろう」
- 集団静観:「みんな動かないから大丈夫」
研究例として、E. L. Quarantelli(1954)は群衆行動の研究で、
危機的状況でも人々がパニックに陥らず“日常の枠組み”に固執する傾向を報告。
またPaul Slovic(1987)はリスク認知の研究で、主観が危険の評価を歪めることを示しました。
結末:避難、そして気づき

恵子:「先生、でも屋根さえ直せば大丈夫ですよね!」
悪もこあい:「次は俺が避難指示を出す。…笑いで。」
健太:「先生、もう研究室が“沈んでる”みたいに見えます…(比喩です)」
もこあい先生:「“大丈夫”は時に一番危ない言葉。次は“変だ”を口に出そう。」
✅ まとめ:今日からできる3つ
- 違和感を言語化:「今、少し変だ」と口に出す(記録も)
- 一時停止のルール:予期せぬ挙動は即・停止&確認
- “みんな”より“自分”:集団静観でも、まず自分が一歩
📚 参考文献・出典
- Quarantelli, E. L. (1954). The Nature and Conditions of Panic. American Journal of Sociology.
- Slovic, P. (1987). Perception of Risk. Science, 236(4799), 280–285.
- 内閣府(2011)「災害時の人間行動に関する調査」
※本記事は教育目的で一般に広く参照される研究を要約したものです。詳細は一次文献をご確認ください。